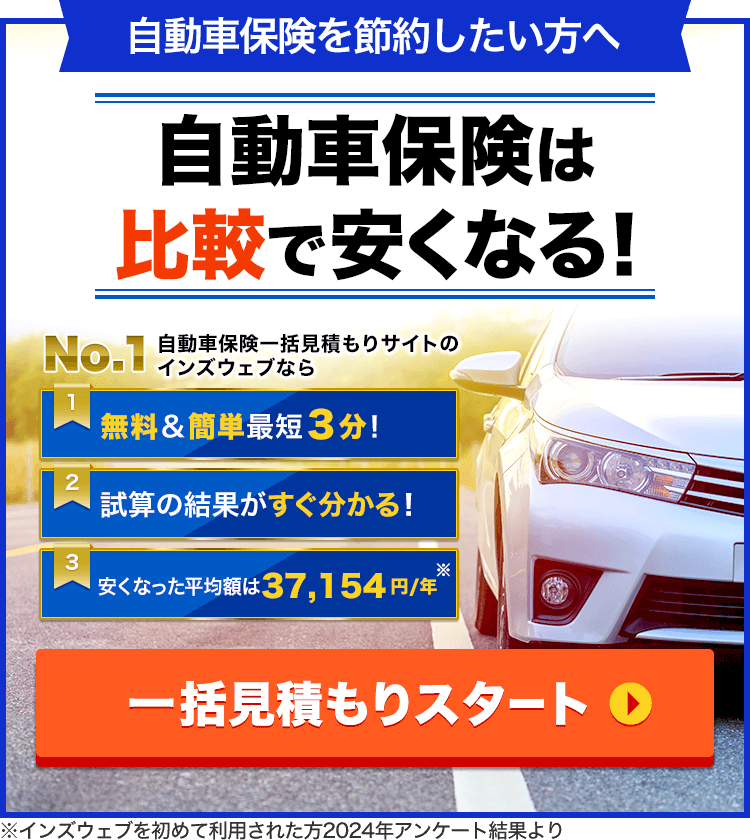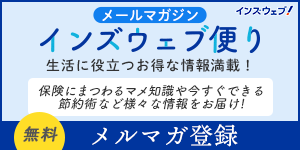今回は、子どもの交通事故についてお話します。子どもの交通事故とは、ここでは、幼児・小学生・中学生が関係した事故のことを言います。子どもの交通事故は、近年、減少傾向にあります。
とはいえ、平成26年上半期(1月~6月)だけで、発生件数は904件あり、子どもの死傷者数は1268名と、決して楽観できる数字ではありません。いつわが子が交通事故に遭ってしまってもおかしくはないのです。
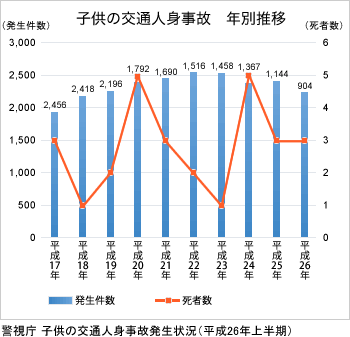
※発生件数…子供が第1、2当事者となった事故の合計件数 ※死者数、負傷者数…車両同乗等を含む子供の被害者数
ところで、子どもの交通事故といえば、飛び出しや信号無視など、子どもの不注意に起因する事故も多いイメージがあります。一般に、交通事故が起きた場合で被害者にも不注意がある場合には、過失相殺といって、損害賠償額が減額されます。
では、子どもの不注意が原因で交通事故が起きた場合にも、同じように損害賠償額が減額されるのでしょうか。そもそも過失相殺とはなぜされるのでしょうか。
交通事故と過失相殺
まず、過失相殺について説明します。加害者が故意または過失によって適切な運転等をしなかったことで、被害者に損害を与えると、加害者はその損害を賠償する義務を負います。
しかし、わき見運転をして被害者を死亡させてしまった事案で、歩道を歩いていた歩行者を死亡させた場合と、左右を見ずに突然車道に飛び出してきた歩行者を死亡させた場合とで、賠償金額が同じだとしたら公平ではないでしょう。
後者の場合には、突然飛び出した歩行者にも責められるべき点があるといえます。そこで、このような場合に損害の公平な分担をするため賠償額を減額しようというのが、過失相殺です(民法第722条第2項)。具体的には、過失相殺率や過失割合に応じて賠償額が減額されます。
過失相殺における過失の意義
子どもの交通事故は、グラフを見るとわかるように、平成17年以降、減少傾向にありますが、毎年一定数の死者がいるのが現状です。他のデータでは、時間帯別では、夕方4時から6時の事故が多く、年齢層別では、小学生の事故が多いという結果が出ています。また、自転車乗用中の事故が、56.3%を占めており、歩行中の事故より多くなっています。
さらに事故類型別の発生状況でみると、自転車の事故では、安全不確認や一時不停止などを原因とする出会い頭事故が多く、歩行者の事故では、飛び出しによる事故が多いようです。
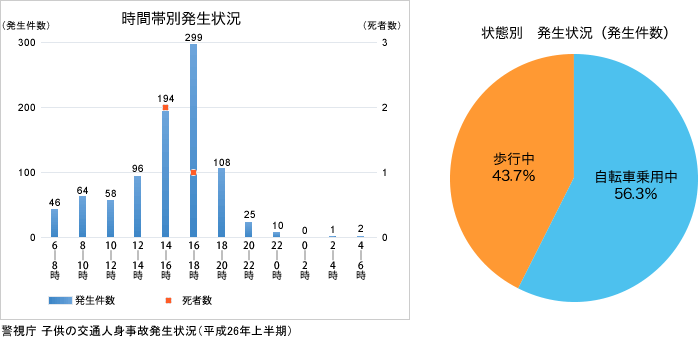
子どもの責任能力(事理弁識能力)
上でみたように、子どもの交通事故の場合、子ども自身の行動が関係している事故は多くあります。このうち、例えば2歳や3歳の子どもがその危険性が全くわからず道路に飛び出してしまった場合のように、物事の善し悪しが分からない子どものであれば、その子を不注意だと責めることはできません。そのようなケースでは、子ども自身の不注意を理由に過失相殺することはできないと考えられています。
それでは、どのような場合に子どもの行動が過失相殺として考慮されるのでしょうか。
この問題に関して、最高裁は、まず、被害者に「事理弁識能力」があれば、過失相殺できると判断しました。事理弁識能力とは、道理をわきまえる能力という意味です。つまり、物事の善し悪しが一定程度分かるのであれば、過失相殺をしてよいと判断したのです。具体的には、5歳ないし6歳で事理弁識能力が備わると判断している裁判例が多くあります。
被害者側の過失
最高裁は、さらに次のような判断も示しました。すなわち、被害者本人に事理弁識能力がなくても、「被害者側」に過失があれば、過失相殺してよいというものです。「被害者側」とは、「被害者と身分上ないしは生活関係上一体をなすとみられるような関係にある者」のことをいい、例えば幼児の父母などです。
この判断からすると、母親が目を離したすきに、一緒に歩いていた3歳の子が道路に飛び出して交通事故に遭った場合、母親の不注意があるとして過失相殺がされてしまう可能性があるのです。
まとめ
このように、子どもが被害に遭う凄惨な交通事故の場合にも、過失相殺によって賠償金額が減額されてしまう可能性があります。
まず第一に子どもが交通事故に遭わないように、そして万一の際に過失相殺されてしまわないように、日頃から、道路での危険な行動や交通ルール・マナーについて繰り返し教えるなどしておくことが大切です。
もちろん、車を運転される方々が、子どもの存在や飛び出しの可能性を常に念頭に置いて、安全運転を心がけていただくことは、もっと大切です。