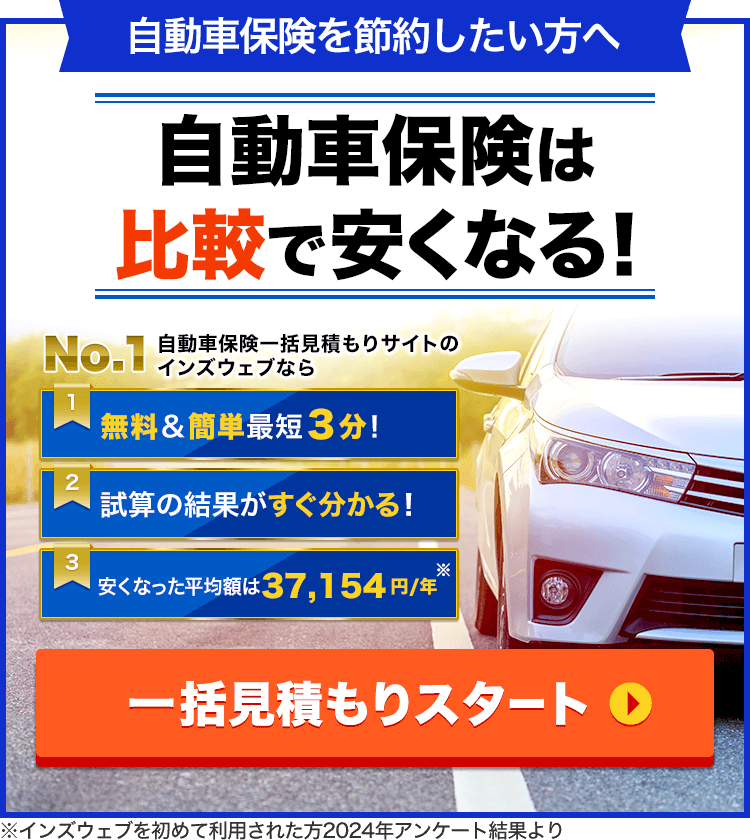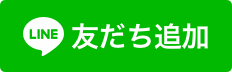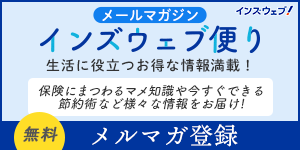2020年に厳罰化された「あおり運転」は、他の車両との車間距離を極端に詰めたりクラクションで威嚇したりして運転を妨害する行為で、誰でも当事者になりうる行為です。自分があおり運転をしないようにするのはいうまでもありませんが、「あおり運転をされる運転」を無意識的にしている場合もあります。自分の運転が原因で、あおり運転の被害者になる可能性もあることに注意しましょう。
また、あおり運転に遭ったときの対処の仕方についても知っておきたいところです。
この記事では、あおり運転の種類とあおられる原因となる行為のほか、対処法と予防策について解説します。
もくじ
あおり運転とは?
あおり運転とは、他の車両の通行を妨害する運転行為のことで、法的には「妨害運転」といわれています。近年、あおり運転による重大な事故が社会問題化するまで、法律上の定義は存在しませんでしたが、2020年に道路交通法の改正により明確に定義され、新たに罰則が設けられました。具体的な要件と罰則は、下記のとおりです。
| 種類 | 要件 | 罰則 |
|---|---|---|
| 妨害運転(交通の危険のおそれ) | ・他の車両等の通行を妨害する目的で行われていること ・行われた行為が、「一定の違反行為(10類型の違反行為)」であること ・道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法であること | ・3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 ・違反点数25点の加算で免許取消処分(欠格期間は2年、前歴や累積点数がある場合には最大5年) |
| 妨害運転(著しい交通の危険) | ・上記妨害運転(交通の危険のおそれ)の罪を犯していること ・高速道路で他の車両を停止させるなど、道路における著しい交通の危険を生じさせたこと | ・5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 ・違反点数35点の加算で免許取消処分(欠格期間は3年、前歴や累積点数がある場合には最大10年) |
法律による厳罰化が実現したことで、あおり運転の抑止力になっているとはいえ、検挙者がゼロになったわけではありません。誰もがあおり運転の当事者になる可能性がある点に、注意が必要です。
妨害運転(あおり運転)の対象となる違反行為
あおり運転には、対象となる10種類の「一定の違反行為」があります。他の車両の通行等を妨害する目的でこれらを行い、道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法であった場合、あおり運転として認定される可能性があります。具体的には、下記のとおりです。
| 違反の種類 | 具体的な違反例 |
|---|---|
| 通行区分違反 (道路交通法第17条第4項) | 対向車線からの接近や逆走 |
| 急ブレーキ禁止違反 (道路交通法第24条) | 不必要な急ブレーキ |
| 車間距離不保持 (道路交通法第26条) | 極端に車間距離を詰めて接近 |
| 進路変更禁止違反 (道路交通法第26条の2第2項) | 急な進路変更や蛇行運転 |
| 追い越し違反 (道路交通法第28条第1項又は第4項) | 左車線からの追越しや無理な追越し |
| 減光等義務違反 (道路交通法第52条第2項) | 不必要な継続したハイビーム |
| 警音器使用制限違反 (道路交通法第54条第2項) | 不必要な反復したクラクション |
| 安全運転義務違反 (道路交通法第70条) | 急な加減速や幅寄せ |
| 高速自動車国道等最低速度違反 (道路交通法第75条の4) | 高速自動車国道などの本線における低速走行 (高速自動車国道の法定最低速度は時速50km) |
| 高速自動車国道等駐停車違反 (道路交通法第75条の8第1項) | 高速自動車国道などにおける駐停車 |

出典:警察庁「STOP!あおり運転!!」、道路交通法第百十七条の二の二
あおり運転に遭う原因となる行為
あおり運転にはできる限り遭いたくないものですが、自分の運転次第で、みずからあおられる原因を生み出してしまうかもしれません。ここでは、あおり運転に遭う原因となりかねない行為について解説します。
右側車線走行時の速度が遅い
あおり運転に遭う原因となる行為のひとつに、右側車線走行時の速度が遅い運転が挙げられるでしょう。
右側車線(追越し車線)を走り続けるのは、本来、道路交通法第20条における「通行帯違反」であり、罰則の対象となります。
なおかつ、中には法定速度より遅い速度で「車線居座り」する車もいます。このような運転は、後続車のフラストレーションを生み、あおられる原因となる可能性が高いのです。
右側車線は基本的に追越し用の車線なので、追越しが終わり次第、すみやかに左側車線に移りたいところです。
車線・進路変更や停止の方法が不適切
あおり運転に遭わないようにするためには、車線・進路変更や停止を適切に行う必要があります。反対にいえば、車線・進路の変更や停止の仕方に問題があると、あおり運転に見舞われる原因となりえます。
具体的には、進路変更の際にウインカーを出さなかったり、赤信号に差し掛かる際に非常にゆっくりとしたスピードで止まったりする運転です。このような運転は、周囲のドライバーを驚かせたりいらいらさせたりして、あおり運転をされるリスクが高まります。
車両後方を確認していない
車両後方をドアミラーやルームミラーといったバックミラー、または目視でよく確認せずに運転していると、あおり運転に遭うリスクが高くなります。後方を確認していない運転は、悪意なく後続車の進路を妨害して割り込んでいたり、急ブレーキを踏ませたりしている可能性があるからです。
運転中は前方だけでなく、こまめに側方・後方を確認するよう意識し、周囲の状況を常に把握するようにしましょう。車線変更や駐車の際以外でも、バックミラーを使ってチェックする習慣をつけることをおすすめします。
あおり運転の対処法
万が一、あおり運転に遭った場合、どのように対処するのがいいのでしょうか。ここでは、あおり運転の対処法について解説します。
早めに道を譲る
早めに道を譲るのは、あおり運転の対処法のひとつとして挙げられます。
右側車線を走っている際に後続車があおってきた場合には、安全を確保しながらできる限り早く左側車線に移り、先行させます。
スピードを上げてあおり運転から逃げようとしたり、一度抜かせてからあおり返したりする行為は非常に危険です。また、あおり運転の相手を運転中にスマートフォンなどで撮影することも、道路交通法違反に該当するため避けましょう。あおり運転に遭ったときには、心の余裕を持って道を譲るのが安全といえます。
人目の多い場所に停止して避難する
あおり運転の対処法として、高速道路であればパーキングエリア・サービスエリア(PA・SA)、一般道であれば道路沿いの店舗の駐車場などへ入り、停車して避難することも効果的です。
駐車する際には、できる限り人目の多い場所を選んでください。高速道路の路肩や非常駐車帯に停車するのは人目がなく、また後続車に追突されるおそれもあるので、避けたほうが賢明です。
相手が近づいてきても車外に出ず通報する
あおり運転に遭って道を譲ったり停車したりしてもしつこく追ってきて、車を降りた相手が抗議しにくるケースもあります。そのような場合には、車外に出たり、窓を開けたりしないようにしましょう。
相手の恫喝や挑発などによって身の危険を感じた際には、ためらわず110番通報して、警察を呼んでください。ドライブレコーダーが搭載されていれば、録画映像があおり運転の有力な証拠になる場合があります。
スマートフォンで相手の行動を録画するのも1つの手ですが、かえって相手を刺激する場合もあるので見極めが必要です。
あおり運転の予防策
あおり運転に遭わないためには、適切な運転を心掛けて、みずから原因を生み出さないようにする必要があります。最後に、あおり運転の予防策について解説します。
左側車線を走行する
道路交通法では、二車線以上の道では左側車線を走行する「キープレフト」が義務付けられています。右側車線に出て追越しする際には、必ず周囲の状況をよく見て、安全な距離を確保しながら車線変更するようにしてください。危険な割り込みなどと捉えられると、相手からの制裁的な措置としてあおり運転を受ける可能性があるからです。
あおり運転のリスクを軽減するためにも、追越し時以外は左側車線を走りましょう。
バックミラーをよく確認する
車のバックミラーで後方をよく確認することで、あおり運転の原因となる行為をせずに済むようになるでしょう。スピードを出して追いついてくる車に早く気づいたり、頻繁な車線変更を繰り返す車を早期に発見できたりします。
なお、車を運転する際には道路交通法第70条で定められた「安全運転義務」の遵守が求められますが、車の左右や後方に対する不確認で起きた事故は「安全不確認」とされ、罰則の対象となるので注意してください。
急停止しない
赤信号などで車を停める際には、急なブレーキをかけて停止することは避けましょう。
前述のとおり、危険回避目的を除き、急ブレーキをかけることは道路交通法で禁止されているため、自分があおり運転の加害者と見なされる可能性があります。
また、「先行車が急ブレーキで嫌がらせをしてきた」と後続車の怒りを生み、さらなるあおり運転を誘発しかねません。交差点などの停止線直前を目指して、適切に速度を落としながら止まるようにしてください。
車間距離を十分に保つ
車間距離を十分に保つことも、あおり運転の予防策として挙げられます。
先行車との車間距離を無意識的に詰めすぎていると、先行車が「あおられた」と受け取ることがあります。その場合、仕返しとして反対にあおり運転を受ける可能性があるので、車間距離の保持には十分注意しましょう。
また、そもそも車間距離を十分に保っていないと、先行車の急ブレーキによる追突事故のおそれもあります。
ドライブレコーダーを装着する
ドライブレコーダーを装着することで、万が一、あおり運転をされた場合にも状況を録画することができます。録画した映像は、事故に遭った場合の証拠として、また事故対応のスムーズな対応にも役立ちます。
また、「ドライブレコーダー録画中」というステッカーを貼ることで、あおり運転の抑止力としても効果を発揮するでしょう。
契約できる保険会社は限られるものの、自動車保険の中にはドライブレコーダーを保険会社からレンタルできる「ドライブレコーダー特約」のあるものもあります。これを付帯することにより、あおり運転予防に一役買うかもしれません。
思いやりを持った運転と事前の備えが大切
ただ愉悦のためにあおり運転をするというケースもありますが、何らかの行為が怒りの引き金となってあおり運転を招くということが多いです。避けられないようなことがきっかけとなることもありますが、追い越し車線をゆっくりと走るなど周りの迷惑となるような運転がきっかけとなることも多いです。自分があおり運転の当事者となる可能性を減らすためにも、思いやりを持った運転を心がけるようにしましょう。
また当事者になったときの備えとしても、ドライブレコーダーを装着することをおすすめします。ドライブレコーダーで録画していることが分かればあおり運転の抑止にも働きますし、実際にあおられてしまったらその証拠となります。自前でドライブレコーダーを用意するのでもよいですし、契約する自動車保険にドライブレコーダー特約があればそちらでもよいでしょう。
自動車保険の補償内容を複数の保険会社で比較・検討する際には、インズウェブの「自動車保険一括見積もりサービス」が便利です。複数社の見積もりを一度に取れるので、比較・検討がしやすくなります。
ぜひ、インズウェブの「自動車保険一括見積もりサービス」をお試しください。