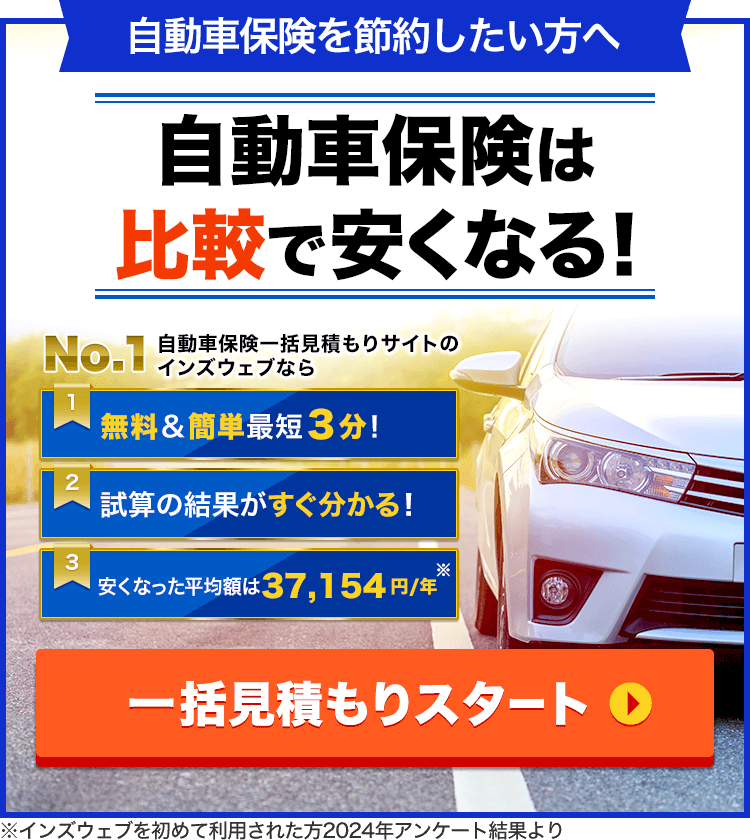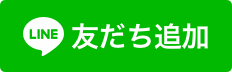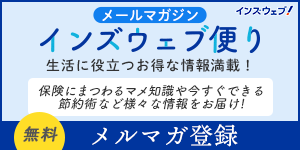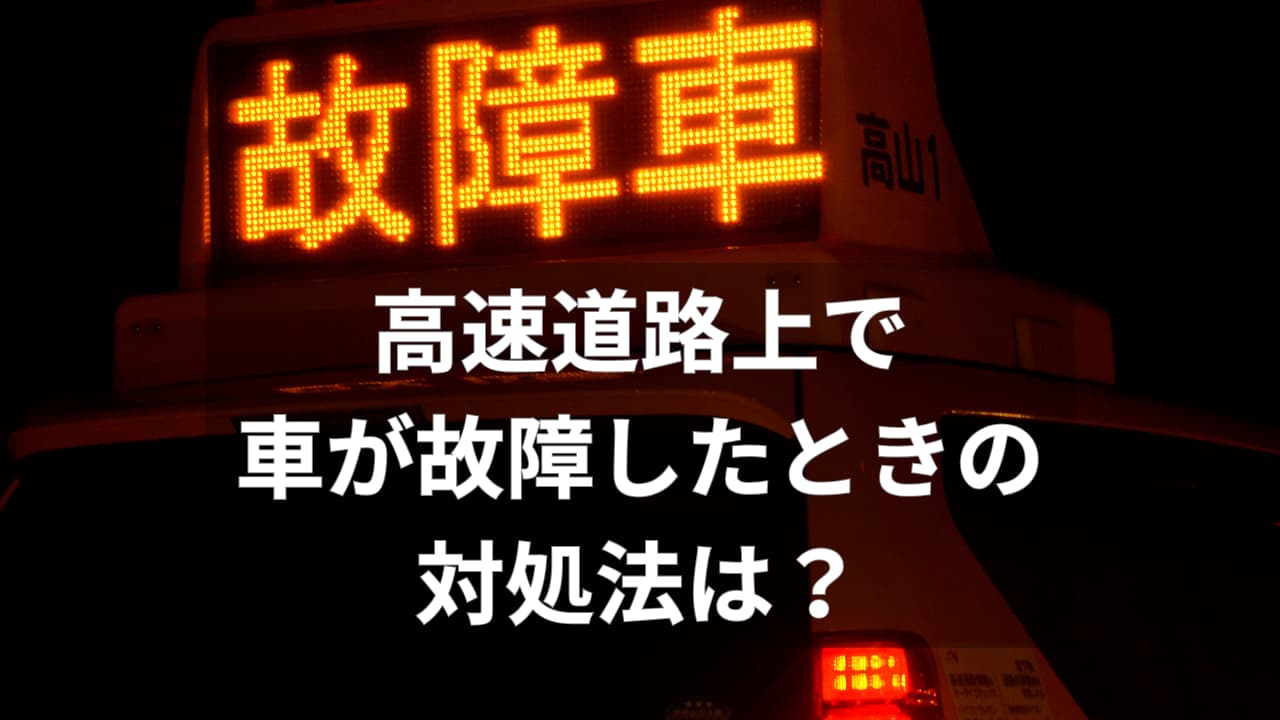
高速道路上で車のタイヤがパンクしたり、渋滞中にエンジンがオーバーヒートしたりした場合、どのように対処すればいいのでしょうか。多くの車が高い速度で走る高速道路上では、故障の際に適切な対処を行わないと、二次的な事故が起きる可能性もあるので注意が必要です。
この記事では、高速道路上で車が故障したときの対処法とよくある故障原因のほか、故障時の連絡先について解説します。
もくじ
高速道路上で車が故障した際の対処法
車が高速道路を走っているときに故障した場合、どのように対処すればいいのでしょうか。ここでは、高速道路上で車が故障した際の対処法について、順を追って解説します。
1.ハザードランプの点滅
高速道路上で車の故障や異変に気づいたら、まずは赤いハザードスイッチを押し、ハザードランプを点滅させてください。ハザードランプは正式には「非常点滅表示灯」といい、方向指示器(ウインカーランプ)を同時に点滅させる装置です。周囲に対する意思表示ができる手段として、効果を発揮します。
ハザードランプの点滅によって後続車に異常を知らせ、追突事故を防ぐようにしましょう。ちなみに、エンジンが故障してもハザードランプは作動可能です。
2.安全な場所への車両移動
次に、後続車の追突リスクに備えるために、急ハンドルや急ブレーキは避けながら、できる限り安全な場所に車両を移動させます。これは、道路交通法第75条の8にも定められている「高速道路の駐停車禁止」の例外的措置です。具体的には、高速道路上の左側にある路肩・路側帯や非常駐車帯のほか、サービスエリア(SA)やパーキングエリア(PA)などへ動かしてください。
車のエンジンが停止して自走が困難な場合でも、少しでも安全な場所に動かし、本線上には止まらないようにしましょう。停車時にはハンドルを路肩側に切るようにすれば、後続車が追突した際に車両が本線側へ押し出され、他車と衝突するのを防ぐなど、二次的被害を最小限にとどめることができます。
3.三角表示板と発煙筒の設置
故障車を安全な場所に停めたら、車両から50m以上後方に、後続車への危険を知らせる三角表示板を路面に対して垂直に設置します。後続からの追突を避けるためには、車に備え付けられた発煙筒も併せて使用します。発煙筒は、三角表示板より後方に設置しましょう。
なお、発煙筒は、トンネル内や燃えやすいものが近くにある場合には使用しないでください。また、緊急時における三角表示板の高速道路上での設置は法的義務ですが、発煙筒と違って車の標準装備品ではないため、注意が必要です。
4.避難による安全確保と救援要請
最後に、故障車から離れ、ガードレールの外など安全な場所に避難します。後続車による追突に巻き込まれる可能性があるため、決して車内に残ったり、車両の近くにとどまったりしないようにしてください。車を降りて、車両後方に避難するのが基本です。
安全を確保したら、携帯電話で「110番」や「119番」のほか、「道路緊急ダイヤル(#9910)」に連絡し、救援を要請します。JAF(一般社団法人日本自動車連盟)や加入保険会社のロードサービスへの連絡も有効です。
携帯電話による救援要請の際には、故障車の位置を正確に伝えるため、路肩に設置されたキロポストや周辺の目印を確認しておきましょう。山間部などで携帯電話の電波が通じない場合は、1kmごとに設置された非常電話(トンネル内は200mごとに設置)を利用してください。
高速道路で車が故障した際の連絡先
高速道路で車が故障した場合は、主に下記の連絡先へ電話連絡します。
| 連絡先 | 番号・ナビダイヤル | 備考 |
|---|---|---|
| 警察 | 110 | 事故による故障の場合 |
| 救急・消防 | 119 | ケガ人がいる場合 |
| 道路緊急ダイヤル | #9910 | 事故を伴わない場合 |
| JAFロードサービス救援コール | 0570-00-8139 または #8139 | スマートフォンアプリ、FAXでも連絡可能、 会員は基本料や一定のサービスが無料 |
| 保険会社のロードサービス | 各保険会社のフリーダイヤル | 利用は無料 |
高速道路上で発生した事故によって車が故障した場合は、まず警察へ連絡してください。これは事故が起きた場合、警察への連絡が法律で義務付けられていることが理由です。
その上でケガ人がいたり、車両火災などが起きたりした場合には、救急や消防へ連絡しましょう。
高速道路で起きる車の故障の原因
車の故障が高速道路で起きる場合、どのような原因が多いのでしょうか。ここでは、高速道路で起きる車の故障の原因について解説します。
タイヤのパンク・バースト
高速道路で起きる車の故障原因として最も多いのが、タイヤのパンク・バーストです。
JAFが公表した「JAFロードサービス 主な出動理由TOP10 2024年度 年間『四輪・二輪合計』」によれば、高速道路における出勤理由のナンバーワンは「タイヤのパンク、バースト、エアー圧不足」で、全体の約41%に達しています。
東京都周辺の自動車専用道路である首都高速道路でも、年間あたり約1万件の車両故障が発生していますが、そのうちタイヤのパンクが4割を占めているという調査結果(出典:「首都高の故障車発生状況と日常点検のお願い」)が出ています。
タイヤがパンク・バーストすると、車が走行不可能になったり、コントロールできなくなったりするおそれがあります。理由はタイヤの摩耗や空気圧不足であることが多いので、運転前のタイヤ溝や空気圧チェックを忘れないようにしましょう。
バッテリーの不調
バッテリーの不調も、高速道路で起きることが多い車の故障原因です。主に「バッテリー上がり」によって、車が高速道路上の渋滞に巻き込まれたときや、SA・PAで停止してしまうことがあります。
バッテリー上がりは、劣化したり、寿命を迎えたりしたバッテリーに起こるもので、特にエアコンを多用する夏場の渋滞で起きやすくなります。高速道路に入る前に、バッテリーの寿命や容量のチェックが必要です。
エンジンのオーバーヒート
高速道路の渋滞時に起きる車の故障として、エンジンのオーバーヒートが挙げられます。これは、渋滞における低速度の走行によって、エンジンを冷やすラジエターに風が当たらなくなり、冷却水が高温になって冷却機能が作動しなくなることが原因です。
エンジンのオーバーヒートは、場合によっては車両火災につながるリスクもあります。エンジンオイル漏れなども含めた日常的な点検を行っておきましょう。
燃料切れ(ガス欠)
燃料切れ(ガス欠)も、高速道路上の車の故障原因として多く見られます。高速道路に乗る前に給油ランプ(正式名称:燃料残量警告灯)を確認し、残量が少なければ最寄りのSA・PAで給油してください。
なお、高速道路上で燃料切れによって車を停止させた場合、道路交通法違反となり、違反点数2点の加算と反則金9,000円が科せられる可能性があります。
高速道路で車が故障した際に用いるグッズ
高速道路上で車が故障した場合には、二次的な事故を防ぐために「発煙筒」と「三角表示板(停止表示板)」を使用しなければなりません。ここでは、高速道路上で車が故障した際に用いるグッズについて解説します。
発煙筒
後続車に危険を知らせる目的である発煙筒は、正式には「自動車用緊急保安炎筒」といい、車に備え付けられているグッズです。発煙筒などの「非常信号用具」は保安基準によって装着が義務付けられており、これが装着されていない車は車検に通りません。
発煙筒は、キャップを外してマッチのようにすって点火すると赤い炎と煙が出る仕組みで、燃焼時間は約5分間です。夜間に200m離れた距離からでも、確認できるようになっています。
なお、発煙筒には4年の有効期限があります。有効期限が切れた発煙筒は点火しないことがあるものの、車検時に交換義務があるわけではないので注意が必要です。
なお、発煙筒の代わりに非常信号用具として使えるLED非常信号灯も販売されています。
三角表示板
三角表示板は停止表示板ともいわれ、法的には「停止表示器材」と呼ばれている、正三角形の折りたたみ式警告標識です。反射材を使用しているため、昼夜を問わず後続車のヘッドライトに反射して光るのが特徴です。
三角表示板を設置する位置は車両後方50mが基本となっているものの、見通しの悪いカーブや坂道などで故障した場合には、さらに後方に設置して、後続車に気づいてもらう必要があるでしょう。
三角表示板には発煙筒のように携行義務はないものの、高速道路上の故障による緊急停止時には、道路交通法第75条の11に表示義務があります。
これに違反すると「故障車両表示義務違反」となり、下記のような罰則が科されます。
<普通車が高速道路上で故障した際に三角表示板の表示を怠った場合の罰則>
- 反則金:6,000円
- 違反点数:1点
高速道路上で車が故障した際の注意点
高速道路上で車が故障したときの対応として、いくつか気をつけなければならないことがあります。ここでは、高速道路上で車が故障した際の注意点について解説します。
道路上を歩き回らない
車が高速道路上で故障して停止した際に、本線や路肩・路側帯に停めた車の外を歩き回っていると、歩行者の存在に気づかない後続車にはねられるおそれがあります。実際に、事故を起こした車から降りて車線を横切ろうとしたり、携帯電話で救援依頼をしたりしていた人が、はねられて死亡する事故が発生しています。
停車後は本線上を歩かず、できる限り早くガードレールの外など安全な場所へ避難してください。なお、高速道路への歩行者の立ち入り自体は、高速自動車国道法第17条で禁止されています。
三角表示板や発煙筒を設置する際も、後続車の動向を常に確認し、後続車が接近してきたら即座に安全な場所に避難しましょう。
自分で作業しない
高速道路上で故障した車のボンネットを開けてエンジンルームを点検したり、タイヤ交換作業をしたりするのは危険な行為であることに注意してください。時速100kmの車が行き交う高速道路上では、たとえ路肩・路側帯での軽作業でも、重大な事故につながる可能性があるからです。
故障の原因を特定して「自分で修理できそう」と判断しても、JAFやロードサービスの到着を待ち、作業を委ねるようにしましょう。高速道路上という環境では、一般道に比べて何倍もの危険が伴います。
車内に残らない
高速道路上で故障した車の車内にとどまると、後続車に追突された際に衝撃を受けて負傷したり、命にかかわる事故につながったりする可能性があり、非常に危険な行為なので絶対に避けてください。
なお、故障した場所に遮音壁があったり橋梁の上だったりした場合は、道路に沿って避難して非常口を目指します。トンネル内での故障の場合は、近くの非常口や非常駐車帯(750m間隔で設置)に避難します。
高速道路での故障に備えてロードサービスが充実した保険を選ぼう
高速道路上の車の故障は、思わぬ二次的な事故を引き起こすおそれがあります。故障の際には乗員の安全を確保し、関係機関に連絡するなど適切に対処してください。なお、JAFのロードサービスは非会員の場合は有料ですが、加入している保険会社のロードサービスなら基本的には無料で利用できます。万が一に備えて、ロードサービスの内容を確認しておくようにしましょう。
なお、自動車保険のロードサービスの内容は、保険会社によって異なります。自身に合ったロードサービスを探すには、複数の保険会社に見積もりを依頼して、比較・検討してください。
難点としては、各保険会社のウェブサイトで見積もり依頼はできるものの、手間や時間がかかること。そこで、自動車保険の一括見積もりサービスを利用して、手軽に見積もりを依頼するのがおすすめです。
自動車保険の補償内容を複数の保険会社で比較・検討する際には、インズウェブの「自動車保険一括見積もりサービス」が便利です。複数社の見積もりを一度に取れるので、比較・検討がしやすくなります。
ぜひ、インズウェブの「自動車保険一括見積もりサービス」をお試しください。