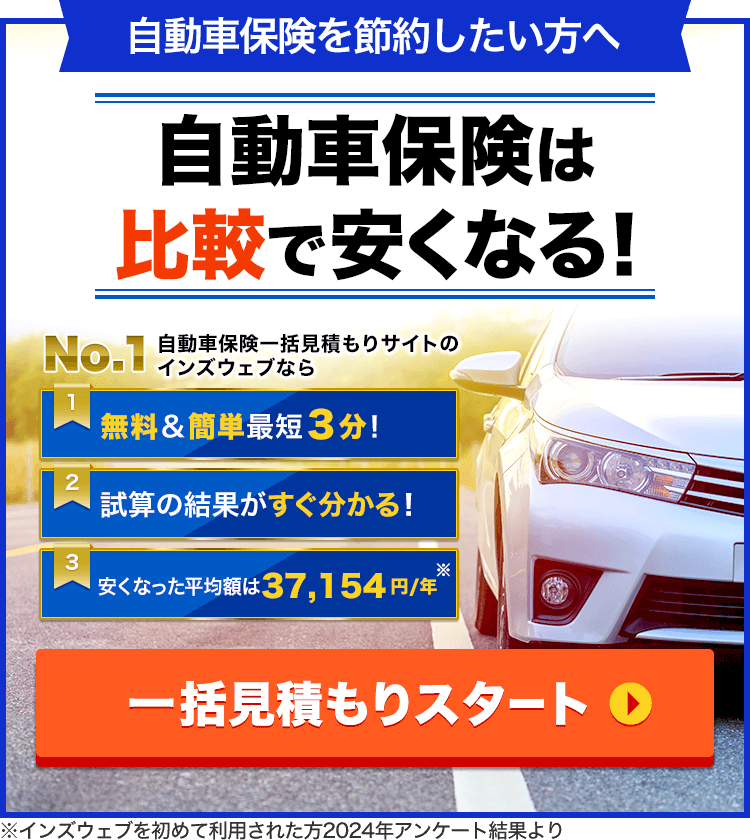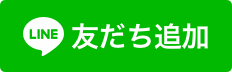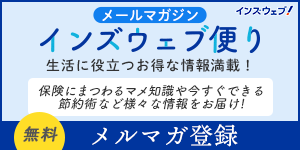車を取得したり所有したりすると、「自動車税」という税金が課せられます。そのうち、車の維持費のひとつといえる自動車税(種別割)は、年間でいくらぐらいかかるものなのでしょうか。また、納付期限や納付方法についてもしっかりと把握しておきたいところです。
この記事では、自動車税の種類や排気量別税額のほか、納付するタイミングと納付方法、自動車税の負担を軽減する方法などについて解説します。
もくじ
自動車税は2種類に大別される
自動車税には大きく分けて、「種別割」と「環境性能割」の2種類があります。なお、環境性能割は2026年4月より廃止される見込みとなっています。まずは、それぞれの違いについて解説します。
毎年4月1日時点の車の持ち主にかかる自動車税(種別割)
毎年4月1日午前0時時点での車の持ち主に課せられるのが、自動車税(種別割)です。「車の持ち主」とは、車検証に記載された車の所有者のこと。カーローンなどで車を購入した場合には、カーディーラーやローン会社が車検証上の車の所有者になるものの、車の使用者として登録された人に税金を納める義務があります。
自動車税(種別割)の税額は、乗用車やトラックといった車の用途ごとに定められています。さらに、車の総排気量や最大積載量などによって細かく区分されているのが特徴です。
なお、軽自動車には、毎年4月1日時点の車の持ち主に軽自動車税(種別割)が課せられます。自動車税(種別割)はナンバー登録した都道府県に納めるのに対し、軽自動車税(種別割)は届出した市区町村に納めます。
車の取得時にかかる自動車税環境性能割
自動車税環境性能割は、車を購入したり譲り受けたりして取得した際にかかる税金です。2026年4月より廃止される見込みです。車の燃費基準や排出ガス基準の達成度に応じて税率が決まるのが特徴であり、これらの環境性能が高いと免税あるいは減税されます。
ちなみに、車を取得した際の金額が50万円以下のときは、課税されない仕組みです。
自動車税(種別割)はいくらかかる?
自動車税(種別割)は車の持ち主に年1回課せられますが、その際に納める税額はいくらになるのでしょうか。ここでは、普通車の自動車税(種別割)と、軽自動車の軽自動車種別割における税額について解説します。
自動車税(種別割)の税額
自動車税(種別割)の税額は、車の用途や総排気量などによって異なります。普通車の場合は、下記のとおりです。
| 総排気量 | 営業用乗用車 | 自家用乗用車 (2019年10月1日以降に初回新規登録の場合) | 自家用乗用車 (2019年9月30日以前に初回新規登録の場合) |
|---|---|---|---|
| 電気自動車 (燃料電池車を含む) | 7,500円 | 2万5,000円 | 2万9,500円 |
| 1L以下 | 7,500円 | 2万5,000円 | 2万9,500円 |
| 1L超1.5L以下 | 8,500円 | 3万500円 | 3万4,500円 |
| 1.5L超2L以下 | 9,500円 | 3万6,000円 | 3万9,500円 |
| 2L超2.5L以下 | 1万3,800円 | 4万3,500円 | 4万5,000円 |
| 2.5L超3L以下 | 1万5,700円 | 5万円 | 5万1,000円 |
| 3L超3.5L以下 | 1万7,900円 | 5万7,000円 | 5万8,000円 |
| 3.5L超4L以下 | 2万500円 | 6万5,500円 | 6万6,500円 |
| 4L超4.5L以下 | 2万3,600円 | 7万5,500円 | 7万6,500円 |
| 4.5L超6L以下 | 2万7,200円 | 87,000円 | 8万8,000円 |
| 6L超 | 4万700円 | 11万円 | 11万1,000円 |
2024年現在、自動車税(種別割)には、地球環境保護を目的とした「グリーン化特例」が設けられています。
グリーン化特例により、環境性能が高い車には税率の軽減措置が適用されます。適用期間内に新車を購入して新規登録を行った場合、翌年度分の自動車税(種別割)が軽減される仕組みです。
具体的には、燃料電池車を含む電気自動車やプラグインハイブリッド車、天然ガス車(2018[平成30]年排出ガス基準適合または2009[平成21]年排出ガス基準NOx10%低減)が該当し、上記基準税額から概ね75%の軽減措置が受けられます。
なお、営業用乗用車については、下記のとおりです。
| 種別 | 排出ガス基準 | 燃費基準 | 軽減率 |
|---|---|---|---|
| ガソリン車またはLPG車 | 2018(平成30)年排出ガス基準50%低減または2005(平成17)年排出ガス基準75%低減 | 2030(令和12)年度燃費基準90%達成かつ2020(令和2)年度燃費基準達成 | 概ね75% |
| 2030(令和12)年度燃費基準70%達成かつ2020(令和2)年度燃費基準達成 | 概ね50% | ||
| クリーンディーゼル車 | 2018(平成30)年排出ガス基準適合または2009(平成21)年排出ガス基準適合 | 2030(令和12)年度燃費基準90%達成かつ2020(令和2)年度燃費基準達成 | 概ね75% |
| 2030(令和12)年度燃費基準70%達成かつ2020(令和2)年度燃費基準達成 | 概ね50% |
軽自動車税(種別割)の税額
現在販売されている軽自動車(四輪以上)は、総排気量が0.66L(660cc)に統一されているため、軽自動車税(種別割)の税額は一律となっています。具体的には、下記のとおりです。
| 種別 | 標準税額 |
|---|---|
| 自家用乗用車 | 1万800円 |
| 営業用乗用車 | 6,900円 |
軽自動車税(種別割)にも、「グリーン化特例」によって高い環境性能を持つ軽自動車の税率を軽減する措置が設けられており、適用期間内に新規検査を行った車に対して、翌年度分の税額が軽減されます。
電気自動車(燃料電池車を含む)や天然ガス車(2018[平成30]年排出ガス基準適合または2009[平成21]年排出ガス基準NOx10%低減)は、上記基準税額から概ね75%の軽減措置を受けられる仕組みです。
なお、営業用乗用車については、下記のとおりです。
| 種別 | 排出ガス基準 | 燃費基準 | 軽減率 |
|---|---|---|---|
| ガソリン車(ハイブリッド車を含む) | 2018(平成30)年排出ガス基準50%低減または2009(平成17)年排出ガス基準75%低減車で2020(令和2)年度燃費基準達成 | 2030(令和12)年度燃費基準90%達成 | 概ね50% |
| 2030(令和12)年度燃費基準70%達成 | 概ね25% |
また、車検証に記載された「初度検査年月」から13年を経過した車に対しては重課措置があり、標準税額の概ね20%アップとなります。
ただし、電気自動車や天然ガス車のほか、ガソリンハイブリッド車とメタノール車、被牽引車は対象外です。
自動車税(種別割)の納付タイミング
自動車税(種別割)は、都道府県の税事務所から5月上旬に送付されてくる納税通知書を使って、5月31日の納期限までに納めます。5月31日が土曜日や日曜日、祝日に当たる場合は、翌週の月曜日が納期限です。ただし、青森県と秋田県は約1ヵ月ずれており、6月上旬に送付され、6月末日までに納付します。
軽自動車税(種別割)は区市町村民税のため、市区町村の税事務所から納税通知書が5月上旬に送付され、5月末までに手続きを行います。
自動車税(種別割)の納付方法
自動車税(種別割)と軽自動車税(種別割)は、さまざまな方法で納付することができます。ここでは、自動車税(種別割)の納付方法について解説します。
ただし、制度の細かい内容は都道府県や市区町村ごとに異なるため、納付前にお住まいの自治体のウェブサイトなどで確認するようにしてください。
金融機関や税事務所窓口などでの納付
自動車税(種別割)は、銀行や郵便局、都道府県税事務所、役所などの窓口のほか、コンビニエンスストアの有人レジなどで現金納付が可能です。送付された納税通知書兼納付書に印字されたバーコードを読み取ってもらい、定められた税額を納付します。その際、「領収日付印」欄に領収印(証明印)が押されたものは、「納税証明書」として有効になります。
口座振替(自動払込)での納付
自動車税(種別割)は、口座振替(自動払込)での納付も可能です。銀行や郵便局などの金融機関の預貯金口座から自動で引き落とされるため、窓口へ行く手間が省けたり、納付漏れを防げたりするのがメリットといえます。
口座振替をするには、預金通帳と届出印、車のナンバーがわかる車検証などを持って、自治体の口座振替申込書に必要事項を記入・押印し、窓口で申し込みます(郵送による手続きが可能な自治体もあります)。申込期限は2月末あるいは3月末までなので、注意が必要です。
クレジットカードによる納付
多くの自治体では、クレジットカードを使って自宅や外出先で自動車税(種別割)を納付することも可能です。
クレジットカードによる納付を行う際には、パソコンやスマートフォンで地方税共同機構が運営する地方税お支払サイトにアクセスします。納税通知書に印刷された「eL-QR(2次元コード)」を読み取るか、「eL番号」を入力して、手続きを行う仕組みです。
クレジットカードによる納付のメリットは、クレジットカードのポイントが貯められたり、24時間いつでも納付できたりする点にあります。また、クレジットカードの分割払い機能を活用した分割払いも可能です。ただし、地方税お支払サイトでクレジットカード払いを利用すると、システム手数料(決済手数料)が発生するので注意してください。
スマートフォン決済アプリによる納付
納税通知書や納付書に印刷されたコンビニエンスストア収納用2次元バーコード(QRコード)を、スマートフォン決済アプリで読み取って決済することで、自動車税(種別割)や軽自動車種別割を納付できます。手数料は無料です。
なお、利用可能なスマートフォン決済アプリは自治体によって異なりますが、主に下記のようなものがあります。
<納付に利用できる主なスマートフォン決済アプリ>
- PayPay
- F-REGI 公金支払い
- PayB
- au PAY
- ファミペイ
- 楽天銀行アプリ
- モバイルレジ
Pay-easy(ペイジー)による納付
Pay-easy(ペイジー)は、パソコンやスマートフォンで公共料金や携帯電話、ネットオークションなどの代金を支払うことができるサービスです。このペイジーを使って、手数料をかけずに自動車税(種別割)を納付することができます。
ペイジーマークが印刷されている納税通知書または納付書を使って、インターネットバンキングかペイジー対応型銀行ATMで納付手続きを行います。インターネットバンキングを利用する際には、金融機関との契約が事前に必要なので注意しましょう。
自動車税(種別割)に関する注意点
自動車税(種別割)に関しては、いくつか気をつけておきたいポイントがあります。ここでは、自動車税(種別割)に関する注意点をご紹介します。
一定以上の年数が経過した車は重課される
自動車税(種別割)あるいは軽自動車種別割は、優れた環境性能を持つ車に対して税率を軽減する一方で、新規登録あるいは新規検査から一定年数を経過した車に対しては、税率を重くする特例措置を設けています。
乗用車の場合、ディーゼル車は11年以上、ガソリン車・LPG車は13年以上経過すると、概ね15%重課されるので注意が必要です。重課される税額は、以下のとおりです。
| 総排気量 | 営業用乗用車 | 自家用乗用車 |
|---|---|---|
| 1L以下 | 約8,600円 | 約3万3,900円 |
| 1L超1.5L以下 | 約9,700円 | 約3万9,600円 |
| 1.5L超2L以下 | 約1万800円 | 約4万5,400円 |
| 2L超2.5L以下 | 約1万5,800円 | 約5万1,700円 |
| 2.5L超3L以下 | 約1万8,000円 | 約5万8,600円 |
| 3L超3.5L以下 | 約2万500円 | 約6万6,700円 |
| 3.5L超4L以下 | 約2万3,500円 | 約7万6,400円 |
| 4L超4.5L以下 | 約2万7,100円 | 約8万7,900円 |
| 4.5L超6L以下 | 約3万1,200円 | 約10万1,200円 |
| 6L超 | 約4万6,800円 | 約12万7,600円 |
軽自動車種別割の場合、概ね20%重課され、以下のようになっています。
| 種別 | 重課税額 |
|---|---|
| 自家用乗用車 | 1万2,900円 |
| 営業用乗用車 | 8,200円 |
未納の場合には車の売却ができない
自動車税(種別割)の納税証明書は、車の売却の際に必要になる書類です。自動車税(種別割)の未納によって納税証明書が手元にない場合、車の所有者の名義変更手続きが行えず、結果として売却できないのです。
もし、納付したくても納税通知書や納付書が手元にない場合は、都道府県税事務所などの窓口へ問い合わせましょう。なお、軽自動車は、市区町村役所・役場などの窓口へ問い合わせてください。
また、自動車税(種別割)は納期限を過ぎると、延滞金が発生します。未納期間が長くなると督促状や差し押さえ通知書などが届き、それでも納付しない場合、最終的には預貯金や不動産といった財産が差し押さえられる可能性があります。ですから、自動車税(種別割)は必ず納期限までに納めるようにしてください。
軽自動車は抹消登録しても軽自動車税が還付されない
都道府県に登録した乗用車は自動車税(種別割)を1年分まとめて納税しますが、年度途中で抹消登録(永久抹消登録あるいは一時抹消登録)した場合、5月末に先んじて納めた税金が納税者に還付されます。
一方、軽自動車は、同じように1年分をまとめて軽自動車税(種別割)を納税するものの、年度途中で抹消登録しても、還付されない仕組みになっているので注意しましょう。
自動車税の負担を軽減する方法
自動車税には「種別割」と「環境性能割」の2種類がありますが、これらの税負担を少しでも抑えるには、どのようにしたらいいのでしょうか。ここでは、自動車税の負担を軽減する方法について解説します。
環境性能が高いエコカーを購入する
優れた環境性能を持つ車であるエコカーを購入することで、自動車税の税負担を抑えることができます。
車の購入時にかかる自動車税環境性能割は、電気自動車やハイブリッド車など対象となるエコカーを自家用乗用車として購入することで、税率は0%(非課税)~3%になります。具体的には、下記のとおりです。
| 車種 | 2024年1月1日~2025年3月31日の税率 | 2025年4月1日~2026年3月31日の税率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自家用 | 営業用 | 自家用 | 営業用 | |||
| 電気自動車(燃料電池車を含む) | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | ||
| 天然ガス車(2018[平成30]年排出ガス基準適合または2009[平成21]年排出ガス基準NOx10%低減) | ||||||
| プラグインハイブリッド車 | ||||||
| ガソリン車(ハイブリッド車を含む) | 2018(平成30)年排出ガス基準50%低減または2009(平成17)年排出ガス基準75%低減車で、かつ2020(令和2)年度燃費基準達成車 | 2030(令和12)年度燃費基準95%達成 | 非課税 | 非課税 | ||
| 2030(令和12)年度燃費基準90%達成 | 1% | 非課税 | ||||
| 2030(令和12)年度燃費基準85%達成 | 0.5% | |||||
| 2030(令和12)年度燃費基準80%達成 | 1% | 非課税 | 2% | |||
| 2030(令和12)年度燃費基準75%達成 | 2% | 0.5% | 1% | |||
| 2030(令和12)年度燃費基準70%達成 | 3% | |||||
| 2030(令和12)年度燃費基準60%達成 | 3% | 1% | 2% | |||
| 上記以外 | 2% | |||||
また、前述のとおり、毎年納めることになる自動車税(種別割)も、グリーン化特例によって概ね50~75%(軽自動車税(種別割)は概ね25~75%)が軽減されます。エコカーを購入すると、購入費と維持費の両面で税負担が軽減されるのです。
さらに、自動車関連の税金で、車の重量や種別などに応じて車検ごとにかかる自動車重量税も、エコカーを購入すると「エコカー減税」が適用されるので、通常より25~100%軽減されるメリットがあります。
新規登録・検査から13年が経過する前に乗り換える
自動車税(種別割)と軽自動車税(種別割)は、13年以上経過したガソリン車などに対して約15%(軽自動車は約20%)アップの重課措置が設けられています。自動車税(種別割)の負担を抑えたいなら、新規登録・検査から13年が経過する前に乗り換えたほうがいいでしょう。
なお、自動車重量税についても、新規登録・検査から13年以上と18年以上が経過した車に対する2段階の重課措置が設けられているため、注意が必要です。
普通車は月初めに登録し、軽自動車は4月2日以降に購入する
自動車税(種別割)は毎年4月1日時点の持ち主に1年分が課されます。普通車を年度途中で購入した場合には、購入月の翌月から3月までの自動車税(種別割)を月割りし、新規登録の際に納付します。
例えば、新規登録する日を5月31日にすると6月分の税金から発生しますが、月の初め(6月1日)に登録すると7月分の税金からとなるので、自動車税種別割の納税額をまるまる1ヵ月分抑えることができるのです。
なお、同じく毎年4月1日時点での持ち主に課される軽自動車税(種別割)には、月割りの制度がありません。その代わり、4月2日以降に購入すると、その年度の軽自動車税(種別割)を課されることはないため、1年分の税負担を抑えることが可能になります。
軽自動車や小排気量の車を購入する
自動車税(種別割)は、車の総排気量などに応じて課せられる税金です。そのため、総排気量の小さい車を購入すれば、税負担は抑えられます。
例えば、1L以下の車の自動車税(種別割)は年間税額が2万5,000円であり、1L超1.5L以下の車(3万500円)に比べて、年間で5,500円の差があります。
さらに、660ccの軽自動車の軽自動車税(種別割)は、一律1万800円です。1L以下の車に比べて、年間で1万4,200円もの差が生じます。
総排気量が大きければ大きいほど車の走行性能には余裕が生まれるものの、用途を考えた上で総排気量が小さくても問題がないのであれば、軽自動車や小排気量車の購入がおすすめです。
自動車税を含む維持費を抑えるには、自動車保険も比較・検討しよう
自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の車の持ち主に課せられる税金です。車の用途や総排気量などによって異なりますが、自動車税など自動車関連の税金を含む、車の年間維持費をできる限り抑えたいのであれば、小排気量のエコカーを購入するのがいいでしょう。
なお、車の維持費を抑えるには、自動車保険の年間保険料やサービス内容を比較・検討するのもひとつの手といえます。複数の自動車保険を比較・検討する際には、インズウェブの「自動車保険一括見積もりサービス」が便利です。
複数社の見積もりが一度に取れるので、比較・検討がしやすくなります。ぜひ、「自動車保険一括見積もりサービス」をお試しください。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。