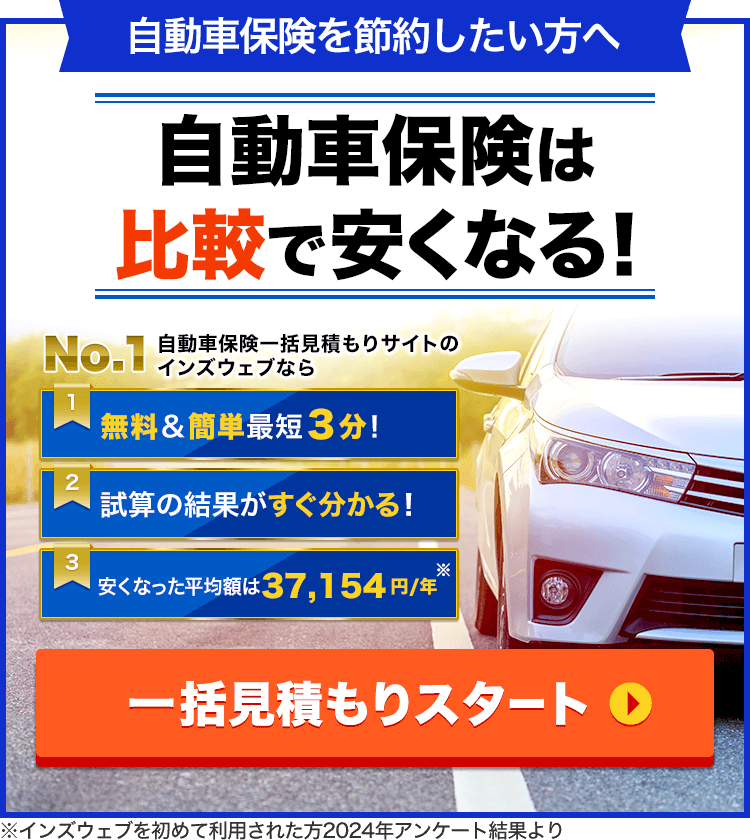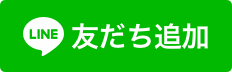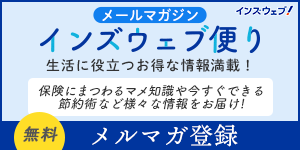通勤や通学の移動手段として、車とバイクのどちらを購入するか迷っている方もいるのではないでしょうか。どちらにもメリット・デメリットはあり、購入費や維持費を含めると大きな買い物となります。ここでは小型車と軽自動車、原付と250ccのバイクを例にして比べていきますので、自分の生活スタイルに合った方を選んでいきましょう。
車のメリット

人や荷物を乗せられる
友人など複数人を乗せる機会が多く、大きな荷物や荷物が多い場合には車が向いています。バイクでも原付以外は二人乗りができるものの、免許を取得して一年経過しないと乗れなかったり、都心部の首都高速道路や一部の道路では二人乗りが禁止されていたりするなど制限があります。
天候や季節に左右されにくい
冷暖房が使用できるため、天候や季節を問わず快適に車内で過ごせます。雨が降っても体が濡れずに移動でき、一年中移動手段として活用できるのが車です。
安全性が高い
毎日の通勤・通学で車やバイクを走行していると事故に遭うこともあるかもしれません。乗車中の交通事故による死傷者の割合はバイクより自動車の方が低いというデータがあります。
| 自動車 | 78,533,241 | 203,749 | 0.26% |
|---|---|---|---|
| バイク | 4,035,432 | 37,334 | 0.93% |
| 保有台数総計 | 乗車中の死傷者数 | 割合 |
バイクは体がむき出しの状態で走行するため、事故による衝突や転倒で大きなケガや死亡に繋がってしまう恐れがあります。事故が起きた時の安全性で比べると、衝撃から身を守ってくれるエアバッグがある車の方が高いといえるでしょう。車によっては衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑制装置、車間距離制御装置などがあり、安全運転を支援してくれる機能が充実していることも。安全性を重視したい方は安全装置がついた車を選ぶことをおすすめします。
車のデメリット
費用が高い
車は車体価格も維持費も高くなる傾向にあります。一般的に普通自動車よりも軽自動車の方が車体価格は抑えられていますが、それでも新車の場合は130万円から200万円は必要になります。バイト代やお小遣いで費用を捻出する学生や、社会人になったばかりでお給料が少ない方には、新車を買うのは厳しいかもしれません。また、税金や車検代、ガソリン代などの維持費も車の方が高くなります。
渋滞に巻き込まれやすい
季節や曜日、時間帯によっては渋滞が発生し、車の場合は渋滞に巻き込まれやすくなってしまいます。通学や通勤で使っている道で渋滞が発生しやすい場合は、時間に余裕をもって出発することや別の道を通る等の対策が必要になります。
バイクは機動性が高く渋滞が発生してもすり抜けができますが、事故を起こしたり車に接触したりするリスクがあるため、道路状況によって注意が必要です。
過失割合が大きくなりやすい
車とバイクでの人身事故が起こった時、バイクに乗っている人の方が大きな被害を受けやすいため、車の過失割合が大きくなることが多いです。バイクに限りませんが、交通弱者である自転車や歩行者に対する事故では車やバイクの過失割合が大きくなります。
なお、過失割合を決めるのは警察ではなく事故の当事者です。交渉に不安がある場合は弁護士に任せることもできます。自動車保険の弁護士費用特約をつけておけば、弁護士への依頼費用が補償されます。万が一事故が起きた時のために、任意保険で備えておくと安心です。
自動車保険に加入するなら一括見積もりがおすすめ!
バイクのメリット

費用が安い
バイクは車体価格や維持費が安く済みます。特に原付は10万円代から購入でき、250ccクラスのバイクでも50万円~100万円ほどの金額です。自動車は車検を受ける必要がありますが、250cc以下のバイクでは車検はないため数万円の費用を節約することができます。税金や車検代、ガソリン代などの維持費もバイクの方が安くなっています。
機動性が高い
バイクは機動性が高く、自動車では慎重に運転しなければならないような狭い道路でも楽に通行できます。小回りが利くため、自動車では大変なUターンや駐停車も簡単にできます。
燃費が良い
バイクは自動車よりも車体が軽いため、燃費が良いのが特徴です。250ccクラスの燃費は30km/Lほど、原付では50km/Lを超えることもあります。燃費が良いとガソリン代も安く済むので経済的といえるでしょう。
バイクのデメリット
荷物があまり積めない
バイクでは多くの荷物を積めません。収納もフロントポケットなどの小物入れがあるもののメットイン(シートの下のヘルメット入れ)がメインとなります。収納を増やすならタンクバッグやシートバッグを付ける、リュックを背負って運転するなどの工夫が必要です。バイクには積載物の長さや幅、重量60kg(原付は30kg)等の積載制限があります。荷物が多くなるとバランスも崩しやすくなるため注意しましょう。
天候や季節に影響される
天気の良い日に乗るバイクは全身で風を感じられて楽しいものですが、雨の日は濡れてしまうためレインスーツやレインカバー等の装備は必須になります。また、ヘルメットに水滴がついて視界が悪くなったり、雨で濡れた道路は滑りやすくなったりするため注意を払って運転しなければなりません。通学や通勤で毎日乗る場合には、悪天候の日の移動手段についても考える必要があります。
また、自動車は冷暖房が付いているため季節に関係なく快適に過ごせますが、バイクは気温がダイレクトに体に伝わります。真夏では直射日光を浴びバイク本体からの発熱もあり熱中症になる恐れもあります。真冬は冷たい風が直撃するため電熱装備による寒さ対策が必須になります。
事故に遭った時にケガをしやすい
どんなに慎重に運転していても、バランスを崩して転倒してしまったり、立ちゴケをしたりしてしまうことがあります。車と違ってエアバッグやシートベルトがないため、ヘルメットやプロテクターを着用して身体を保護しましょう。もし転倒して自分がケガをした場合、自賠責保険では補償されないため、任意保険で備えておくと安心です。
バイク保険に加入するなら一括見積もりがおすすめ!
維持費の種類
車やバイクを購入する際には、車体価格だけでなく維持費にも注意が必要です。そこで、維持費の種類や節約ポイントを紹介します。
税金
車やバイクを購入した後は「自動車税・軽自動車税(種別割)」や「自動車重量税」の2つの税金がかかります。
自動車税・軽自動車税(種別割)は年に1回納める税金です。軽自動車は一律10,800円ですが、普通車やバイクは総排気量によって税額が変わります。
| 用途区分 | 総排気量 | 税額 |
|---|---|---|
| 軽自動車 | 一律 | 10,800円 |
| 普通車 | 1000cc以下 | 25,000円 |
| 1000cc超1500cc以下 | 30,500円 | |
| 1500cc超2000cc以下 | 36,000円 | |
| 2000cc超2500cc以下 | 43,500円 |
| 用途区分 | 総排気量 | 税額 |
|---|---|---|
| 原付一種 | 50cc以下 | 2,000円 |
| 原付二種 | 50cc超~90cc | 2,000円 |
| 90cc超~125cc | 2,400円 | |
| 軽二輪車 | 125cc超~250cc | 3,600円 |
| 小型二輪車 | 250cc超 | 6,000円 |
自動車重量税は車の重さに応じて税額が変わります。車の購入時や車検時に納める必要があります。自動車の場合、新車登録から13年目以降は税額が増えるので中古車を購入する場合は年式に注意しましょう。なお、原付には自動車重量税はかかりませんが、125cc超~250cc以下のバイクは新車登録時に一括で納めます。
| 軽自動車 | 軽自動車以外の自家用乗用車 | |
|---|---|---|
| 新規登録(新規検査)〜12年目 | 3,300円 | 4,100円/0.5t |
| 13〜17年目 | 4,100円 | 5,700円/0.5t |
| 18年目以降 | 4,400円 | 6,300円/0.5t |
| 用途区分 | 総排気量 | 税額 |
|---|---|---|
| 原付一種・原付二種 | 50cc以下 | なし |
| 軽二輪車 | 125cc超~250cc | 4,900円/取得時 |
| 小型二輪車 | 250cc超 | 登録後12年まで1,900円/年 |
保険料
自動車やバイクの保険には、「自賠責保険(強制保険)」と「任意の自動車保険(任意保険)」の2種類があります。自賠責保険はすべての車・バイクに加入が義務付けられている保険で、車の場合は車検時、250cc以下のバイクはコンビニ等で保険料を支払います。しかし、自賠責保険では物損事故や自分や同乗者のケガは補償されず、賠償金額が高額になると対応できません。
そこで、自賠責保険ではカバーできない分を補うのが任意保険になります。任意保険は、補償範囲や運転者の年齢、車種などによって保険料が変わりますが、保険会社によっても保険料が異なります。一般的に、年齢が若く免許を取ったばかりの場合は保険料も高くなりやすいため、一括見積もりで保険会社を比べることで安く加入するのがおすすめです。保険料が気になる方は、インズウェブの自動車保険とバイク保険の一括見積もりサービスを利用して、任意保険料を節約してみましょう。
車検代
原付や250cc以下のバイクでは車検は必要ありません。車では新車を購入した場合は3年後、それ以降は2年おきに車検を受ける義務があります。車の区別や年数、状態によって異なりますが、車検代は数万円〜10万円が相場です。車検代は「法定費用」「車検基本料金」「整備費用」の3つに分かれていますが、法定費用はどの業者に依頼しても差がありません。しかし、車検基本料金と整備費用は幅があり、依頼する業者によって異なります。車検代を抑えるには車検取扱業者の選び方が重要です。
ガソリン代
車やバイクの走行に不可欠なガソリン代ですが、車体が大きく排気量が多くなるほどガソリンの消費量が多くなります。そのため、排気量が少ない原付(50cc)、バイク(250cc)、軽自動車(660cc)、小型車(1500cc)の順でガソリン代が安く抑えられます。毎日の通勤・通学に使う人や運転距離が長い人は低燃費の車種を選びたいですね。
メンテナンス代
車やバイクの維持には定期的なメンテナンスや消耗品の交換も必要になります。タイヤやエンジンオイルなどの交換を定期的におこない、故障やトラブルを未然に防ぎましょう。また、原付や250cc以下のバイクは車検がない分、定期的に点検やメンテナンスをおこなって安全を保っていくことが必要になります。
駐車場代
自宅の敷地内に駐車スペースがない場合や、マンションやアパートの家賃に駐車場代が含まれていない場合には別途駐車場代が必要です。50cc以下の原付は自転車と同じ扱いになるため駐輪場に停めることができますが、賃貸物件の場合は駐輪場が利用できないこともあるため注意が必要です。月極の駐車場代は地域によって大きく異なります。
車とバイク、どちらが安い?
車とバイクの年間維持費はどのくらいかかるのでしょうか。そこで、原付(50cc以下)、軽二輪車(125㏄超~250cc以下)、軽自動車、小型車の4種類の年間維持費を比較してみました。
| 項目 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 原付 | 軽二輪車 | 軽自動車 | 小型車 | |
| 自動車税・軽自動車税(種別割) | 2,000円 | 3,600円 | 1万800円 | 3万500円 |
| 自動車重量税 | なし | 4,900円 | 3,300円 | 1万2,300円 |
| 自賠責保険料 | 6,910円 | 7,100円 | 1万1,140円 | 1万1,500円 |
| 任意保険料 | 5万円 | 6万円 | 8万円 | 9万円 |
| 車検代 | なし | なし | 3万円 | 5万円 |
| メンテナンス代 | 1万円 | 3万円 | 3万円 | 3万円 |
| ガソリン代 | 3万6,000円 | 6万円 | 7万2,000円 | 9万円 |
| 駐車場代 | 6万円 | 6万円 | 12万円 | 12万円 |
| 合計 | 16万4,910円 | 22万5,600円 | 35万7,240円 | 43万4,300円 |
※小型車は総排気量1.0〜1.5Lで車重1.1tのホンダ・フィットを想定。
※自動車税・軽自動車税(種別割)は、2019年10月1日以降に新規登録した車を想定。
※自動車重量税、自賠責保険料は、1年分を想定(税制優遇措置は考慮していない)。
※任意保険料は21歳で初めて契約する場合の相場を想定。
※ガソリン代は150円/Lで、原付50km/L、軽二輪車30km/L、軽自動車25km/L、小型車20km/Lの燃費性能、月間1,000km走行を想定。
※駐車場代はバイク月額5千円、自動車月額1万円を想定。
原付と軽自動車を比べると、原付では約16万5千円、軽自動車は約35万7千円かかり、原付よりも20万円近く維持費が高くなっています。車体価格も含めると、原付と軽自動車にかかる金額の差は100万円以上になるでしょう。
また、バイク同士、車同士を比べてもそれぞれ10万円近く維持費が変わってきます。毎年の維持費も5年乗った場合には50万円近く差がついてくるので、購入の前には自分の希望する車種が維持費がどのくらいかかるかを確認しておきましょう。維持費以外にもそれぞれの特徴を以下にまとめましたので、移動手段としてどれが自分の生活に合っているかを比べてみましょう。
| 原付 | 軽二輪車 | 軽自動車 | 小型車 |
|---|---|---|---|
| ・1人乗り ・高速道路は走行不可 ・小型で扱いやすい | ・2人乗り ・高速道路も走行可能 ・原付よりも車種が多い | ・4人乗り ・小回りが利く ・遠出には向いていない | ・5人乗り ・安全性が高い ・ハイブリッドモデルがある |
毎日使う乗り物ですから、維持費だけで選んでしまうと「こんなはずじゃなかった…」と後悔してしまうことも。運転のしやすさや安全性、友人や荷物を乗せるかどうか等も考慮して、どちらを購入するか検討していきましょう。ぜひ自分に合った車やバイクを選んで、日々の通勤・通学をより楽しいものにしてください。