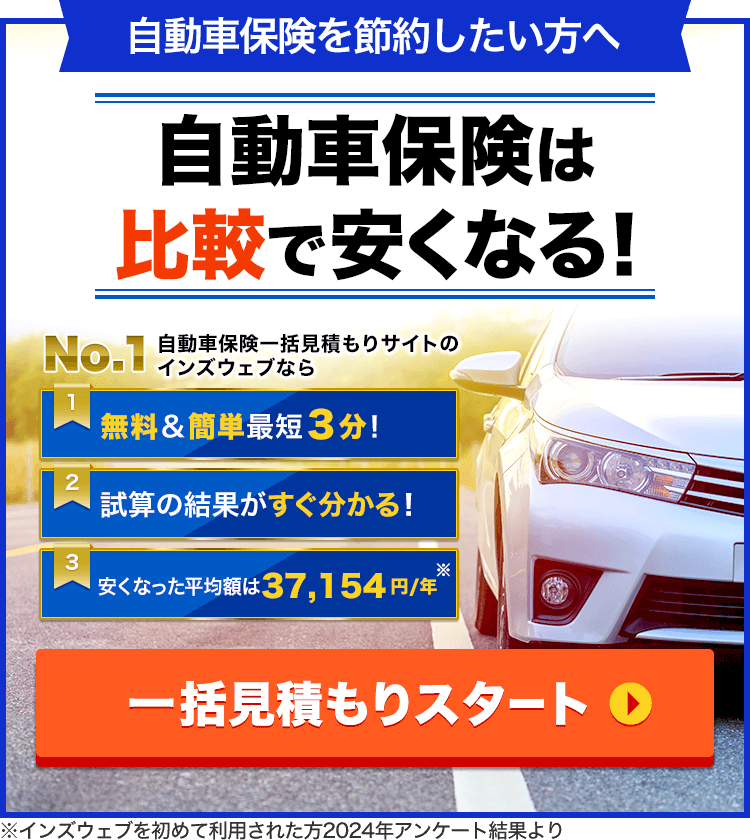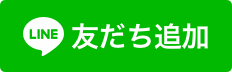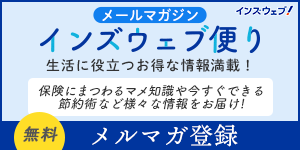生命保険料や社会保険料などの保険料は、年末調整で所得から控除ができますが、自動車保険料はどうなのでしょう。自動車保険料を所得から控除してもらうことができれば節税が可能です。自動車保険料は所得から控除ができるのか、また、自動車保険料を節約する方法について紹介します。
もくじ
自動車保険料は保険料控除の対象外
結論から言うと、自動車保険料は所得控除の対象外で年末調整で控除する事はできません。従って、自動車保険は保険料控除の証明書も発行されません。保険料控除ができる保険契約は決まっており、「保険」で控除の対象とされているものは現在3つです。
ただし、個人事業主が事業用として利用している自動車の保険料に関しては、経費として計上することで事業所得から差し引くことができます。
年末調整とは?
企業に勤める会社員は、従業員の所得税を会社が代わりに給料から天引きして納税しています。所得税や住民税などが毎月の給与や賞与から天引きされていますが、この時点で計算された所得税はあくまで概算で算出された金額で正しい税額ではありません。所得税はその年の1月1日から12月31日までの所得に対して確定になるため再計算し、正しい税額で納税しなおす必要があります。
これまで概算で毎月支払った税額と、1月1日から12月31日までの正確な所得に対して再計算した所得税を比較し、過不足分があれば還付や追徴を行う事を年末調整といいます。
「保険」の中で、生命保険料や社会保険料は控除することができます。支払った生命保険料などは、年末調整を行う際に控除を受けるための申告書が必要になります。
年末調整で受けられる保険料控除
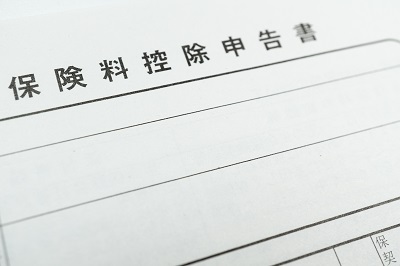
■生命保険料控除
生命保険料控除で対象となる保険は下記の3つです。払い込んだ保険料に応じて、一定の金額が契約者(保険料負担者)のその年の所得から差し引かれます。税率を掛ける前の所得が低くなることにより所得税、住民税の負担が軽減されます。
- 一般生命保険料
- 介護医療保険料
- 個人年金保険料
■社会保険料控除
社会保険料控除は、その年に支払った社会保険料(国民年金・健康保険など)は、全額所得から控除することが可能です。社会保険料控除の対象となる社会保険料を紹介します。
- 国民健康保険料
- 健康保険料(健康保険組合など)
- 国民年金保険料
- 厚生年金保険料
- 国民年金基金の掛金
- 厚生年金基金の掛金
- 介護保険料
- 雇用保険料
- 船員保険料
- 労働災害補償保険料(特別加入者)
- 公務員の互助会費
労働災害補償保険(労災)は、社員が自己負担している分のみが控除の対象です。
■地震保険料控除
火災保険とセットで契約する地震保険があれば、地震保険の保険料は所得控除を受ける事ができます。平成18年の税制改正までは「損害保険料控除」として火災保険料も年末調整・確定申告で所得控除の対象でしたが平成19年分から損害保険料控除は廃止されています。損害保険料控除は廃止となりましたが、地震保険料控除は控除が受けられる保険として現在も対象です。
確定申告をする場合
個人事業主などで確定申告を行う人は、1月1日~12月31日の所得と納める税額を計算し、原則、翌年の2月16日~3月15日のあいだに税務署に報告・納税を行います。確定申告の際に所得控除を受けられる金額を差し引いて所得を申告します。
自動車保険料は所得控除の対象にはなりませんが、個人事業主などは、「自賠責保険(強制保険)」「自動車保険(任意保険)」共に支払った保険料を経費として計上し事業所得から差し引くことが可能です。
事業用として使う車の自動車保険料とは?
個人事業主など事業を行う人が車を事業の用途に使用しているために加入する自動車保険は保険料を必要経費として計上し事業所得から差し引くことが認められています。経費として計上する際には、保険料控除証明書の添付が必要になります。
勘定科目:「損害保険料」または「車両費」で処理
経費計上を行う場合、「自賠責保険(強制保険)」、「自動車保険(任意保険)」共に「損害保険料」という勘定科目で処理を行います。
【自賠責保険】
法律上の加入が義務付けられているため支払った年に全額を経費で計上します。加入期間が1年以上の保険料の支払も支払った年に計上することになります。
【自動車保険】
加入期間が1年間の自動車保険料は自賠責保険料と同じように計上します。加入期間が1年以上ある自動車保険料の支払は、加入年数を分割して毎年計上します(期間按分)。複数年にまたがる自動車保険料は「長期前払い費用」として資産計上します。自賠責保険料とは異なり加入年数を分割して毎年計上する仕組みになっています。
自動車を「事業用」と「自家用」に使っている場合は?
車を事業用としてしてだけで使用しているのではなく、事業用に使わない休日などは自家用車として使っているという場合があります。そういった場合の自動車保険料は、事業用と自家用として使用している按分を計算し経費計上します。
「按分」とは?
按分とは、「どの程度の割合が事業の用途で使用している分になるのか」の「基準の数値」を出して割ることです。月の半分を事業用に使用しているのであれば自動車保険料の按分率は50%です。支払った自動車保険料の50%を事業用として経費計上する事ができます。事業用と自家用に使用されてる車で事業用に使用した割合だけ経費計上を行う事を「家事按分」と言います。自動車保険料を安くする方法
自動車保険料は、年間で数万円から数十万円と家計の出費では大きな固定費になりますが、所得控除の対象外でした。しかし、自動車保険料は安くする方法がいくつかあります。高くなっている要因を取り除いたり、割引制度を利用したり保険会社を比較したりと工夫する事で今よりも保険料を安くできる可能性があります。
1.等級を上げる
保険料を安くするには事故を起こさず等級を上げていくことが大切です。すでに自動車保険を契約している人には今すぐに解決できることではありませんが、親が20等級などの高い等級を持っていて、同居の子供が新しく車を購入する場合などでは、車両入替によって親の等級を子供に譲渡し、親は新規で自動車保険に加入することで保険料の総額を安くすることができます。
年齢が高い親が20等級、低い子供が6等級(あるいは7等級)という状態よりも、親が6等級(あるいは7等級)、子供が20等級という状態の方が保険料が安くなることが想像つきます。単純な運転者の年齢だけでなく、等級が低い方の年齢条件を制限できたり、免許証の色がゴールドであったりすることで保険料を抑えることができます。
なお、等級の譲渡には一定の条件を満たす必要があります。まず、等級の譲渡を行う人と受け取る人が配偶者間か同居の親族間である必要があります。離れて暮らす大学生の子供に譲渡するといったことはできないので注意が必要です。また、そもそも車両入替を利用しているので、家庭で利用する自動車の増車、廃車、返還のタイミングでしか実行できません。すでに保有している自動車間の単純な等級の入れ替えはできないので覚えておきましょう。
2.補償内容を見直す
高くなる理由の中でも書きましたが、補償内容が厚くなれば保険料も高くなります。そのため、保険料を安くするためには、必要以上の補償内容になっていないかの見直しが必要です。対人賠償や対物賠償を削ることは賠償金が億を超えることもあるのでお勧めしませんが、その他の内容については本当に必要なのかもう一度検討してみましょう。
また、運転者限定や年齢条件が適切に設定してあるのか確認してみることもおすすめします。昔加入した条件のまま変更していない場合は、30歳以上の人しか乗らないのに年齢制限なしとなっているなど、補償範囲が必要以上に広くなっているかもしれません。
3.車両保険の条件を見直す
車両保険の有無で自動車保険料は大きく変わりますが、新車の場合など車両保険をつけておきたい場合もあると思います。そのようなときには、車両保険の条件を見直すとよいでしょう。
車両保険は「一般型」と「エコノミー型」の2種類用意されていることが多いです。(保険会社によって名称は異なる場合があります。)「エコノミー型」の場合、補償範囲は狭くなりますが保険料を抑えることができます。
| 一般 | エコノミー | |
|---|---|---|
| 車やバイクとの事故 (相手が判明している場合) | ○ | ○ |
| 自転車との衝突・接触 | ○ | × |
| 電柱・建物などとの衝突や接触 (単独事故) | ○ | × |
| あて逃げ | ○ | △※ |
| 転覆・墜落 | ○ | × |
| 火災・爆発・台風・洪水・高潮など | ○ | ○ |
| 盗難・いたずら・落書き | ○ | ○ |
| 窓ガラスの損害・飛び石による損害 | ○ | ○ |
| 地震(津波や地震起因の火災含む)・噴火 | × | × |
※あて逃げについて、保険会社によってエコノミー型でも補償対象となる場合とならない場合に分かれています。
単独事故などに対する車両保険の補償は必要がないという場合には「エコノミー型」も検討してみるとよいでしょう。なお、補償内容は保険会社によって異なる場合があります。詳しい内容については契約の保険会社にご確認ください。
また、車両保険料を安くするもう一つの方法として、免責金額の設定があります。免責金額とは、簡単に言えば自己負担金額です。車両保険を使う時に免責金額として設定した金額については自己負担で支払います。例えば、免責金額が「5-10万円」(1回目の事故の免責金額が5万円、2回目以降の事故の免責金額が10万円)の設定で1回目の事故の場合で、30万円の修理費用がかかったとすると、5万円は自己負担し、残りの25万円が保険金として支払われます。
この免責金額を「5-10万円」や「10-10万円」など多く設定すれば、保険料を安くすることができます。多少の自己負担は問題ない、少額の修理費用ならば等級のことを考えて車両保険を使わないという場合は、保険料を安くするために免責金額の設定を検討してみて下さい。
-

車両保険の保険料を安くするには
対象の車両にもよりますが、自動車保険は車両保険の有無で保険料が大きく変わります。車両保険は必要だけど保険料を下げたいという場合はここで紹介する内容をもとに保険料を下げることができないか考えてみてくださ ...
4.割引制度を利用する
割引制度を活用することで保険料を安くすることができるかもしれません。保険会社によって様々な割引制度がありますが、利用しやすいものとしては「インターネット割引」です。自動車保険をインターネットから申し込むことで保険料の割引を受けることができます。各社の割引額はこちらで比較できます。また、他の利用しやすいものとしては、「証券不発行割引」があります。紙の保険証券を発行せず、Webページ上で見る形式にすることで保険料を数百円ですが安くすることができます。
そのほかにも、保険会社によって早期契約割引やゴールド免許割引、エコカー割引などの割引が用意されています。自分が契約する保険会社に何か適用できる割引がないか確かめてみてはいかがでしょうか。
-

割引制度を活用して自動車保険料を安くしよう!
自動車保険には一定の条件を満たした場合に割引が適用される制度をとっている保険会社があります。インターネット割引など条件を満たしやすい割引制度もあるので、割引制度をうまく活用できる保険会社と契約すれば自 ...
5.保険会社を見直す
現在代理店型の自動車保険に加入している場合、ダイレクト自動車保険に変えることで保険料を安くすることができるかもしれません。ダイレクト自動車保険は間に代理店を挟まない分、代理店手数料などの費用がかからないので保険料を安くすることができるのです。
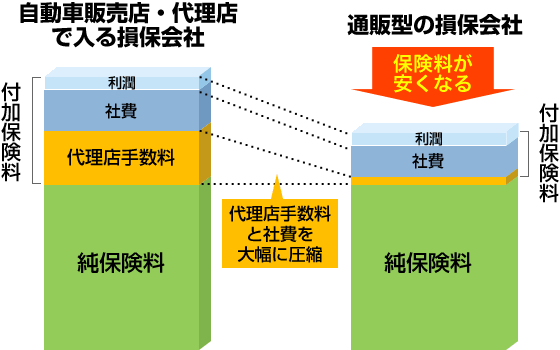
また、ダイレクト自動車保険間であっても、補償内容によってどの保険会社が一番安いのかというは変わってきます。そこで、自分が契約する内容で保険料が安い保険会社を見つけるのには自動車保険一括見積もりサービスが有効です。一度の情報入力で複数の保険会社から見積もりを取得でき、各社の保険料を簡単に比較することができます。各保険会社の見積もりを一つ一つ取るよりも手軽に各社の保険料を知ることができます。一度、一括見積もりを確かめてみてはいかがでしょうか。